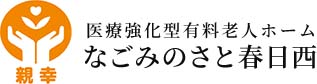2025.5.8
ミニ農園誕生!!
今回は2025年5月の敷地内農園をご紹介します。
なごみのさと春日西に「ミニ農園」が誕生。ご入居者・スタッフの癒しの場所、みんなが集う拠点に!
老人ホーム敷地内に、プランター型ミニ農園が誕生。ご高齢者と集える拠点になればいいな!とスタッフが育てやすく、花が咲いて食べられる植物を植えていました。そのうち数株が花を咲かせ、葉が茂り、実がなり収穫の時期を迎えています。
ねぎが成長しました

博多万能「ネギ」の葉が成長しました。10本ほどですが食べられる大きさです。ねぎは根を残し、土から4~5cmのところで切ると3~4週間でまた収穫できる大きさに成長します。食材高騰の折、月に1回収穫できるのは助かります。冷凍あさりを買ってあさり汁を作りました。ご入居者に振舞うには少量だったので、一部スタッフのお昼ご飯に提供しました。ラーメンを食べているスタッフにも栄養補給で出しました。
ネギは日本では奈良時代に日本に伝わり、古くから食べられている日本人になじみの深い野菜です。11月~2月頃に旬を迎えます。抗酸化作用の高いビタミンCや硫化アリルが含まれており、風邪予防や血行促進、動脈硬化などの生活習慣病の予防にも効果が期待できます。
ニラも成長

「食べる”お薬”」として有名な「ニラ」
ニラは、古くから薬効のある野菜として知られており、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンEなどの栄養素が豊富に含まれています。ニラを食べるとえられる5つの栄養効果です。
1. 免疫力向上
2. 疲労回復
3. 血流改善
4. 冷え性改善
5. 美肌効果
これらの栄養効果に加え、ニラには骨を丈夫にするカルシウムや、便秘解消に役立つ食物繊維なども豊富に含まれています。
旬の春は特に栄養価が高く、ニラ玉やニラ鍋など、様々な料理に活用できます。
ぜひ積極的にニラを食卓に取り入れて、健康的な体作りを目指しましょう。
チューリップ、セージ、カモミール、トマト

「チューリップ」は見た目だけでなく、香り成分も注目されています。チューリップに含まれる主な香り成分はリナロールという成分です。リナロールは、ラベンダーやベルガモットなど多くの植物にも含まれる成分で、血圧を下げ、鎮静安眠効果があり、抗不安作用が働き、リラックスを促す効果があるとされています。またリナロールの抗不安作用についての研究もありました。チューリップの香りに包まれることで、日々の疲れや緊張感を和らげ、穏やかな気持ちになり、忙しい日常に心の安らぎをもたらしてくれるでしょう。
「セージ」には多くの品種がありますが、ハーブとして市販されているのは主にコモンセージの仲間。ヨモギに似た爽やかな芳香を持ち、わずかに苦みがあります。セージがソーセージの語源になったという説があるくらい、特にソーセージづくりによく使われます。抗菌作用に優れ、うがい薬にすることで口や喉のトラブルを解消し、風邪の予防が期待できるハーブです。
また、ホルモンの乱れによるイライラを鎮める鎮静作用もあります。
ドイツの薬草家は、「セージは、医者、料理人にも、台所や地下室など場所も、貧富も問わず役に立つハーブである」といったそうです
「カモミール」は不眠や不安、また、胃のむかつき、ガス、下痢などの胃腸障害に良いとされています。 また皮膚症状やがん治療に起因する口内炎に局所的に使われることもあります。
アトピー、ニキビ、湿疹、あせも、乾燥などの緩和効果が期待できます。 抜け毛を防いで毛髪にツヤやハリを与える効果もあるため、シャンプーによく利用されます。 風邪の初期症状や月経痛をやわらげる効果 カモミールティーは、体を温め発汗させる作用があるので、風邪の初期症状を緩和する薬茶として利用されています。
真っ赤な「トマト」には栄養がいっぱい。その中でも今とくに注目されているのがリコピンと呼ばれるかカロテノイドの一種。トマトの赤い色はこのリコピンの赤なんです。このリコピンですが、生活習慣病予防や老化抑制にも効果があるとか。もっともその研究は比較的最近はじめられたものでその未知のパワーの全容はすべて解明されているわけではありません。しかし、今までの研究からさまざまなリコピンのパワーが解明されています。
ブルーベリー、アザレア

「ブルーベリー」には、ビタミンC・ビタミンE・アントシアニンなどの強力な抗酸化物質が豊富に含まれます。 これらは、活性酸素を抑え、肌の老化予防にも欠かせない栄養素や機能成分です。 ビタミンCは、肌の構成成分であるコラーゲンの生成に必要なほか、皮膚のメラニン色素の生成を抑える効果もあります。ブルーベリーの効果は次のようです。
1.認知症予防
2.眼精疲労に
3.花粉症の予防
抗酸化物質の中には、アレルギー反応の原因となる「ヒスタミン」を抑える働きが期待されているものも多く存在します。
体が本来もつ免疫力は、加齢とともに低下していきます。
抗酸化物質を意識して摂取し、体がもつ免疫機能の老化を予防することで、花粉症の予防にも繋がるでしょう。
アザレアの花

アザレアの花が咲きました。
「アザレア」は、アゼリアや西洋ツツジやオランダツツジとも呼ばれています。
日本では、ツツジというと花壇に植えられていることも多く、幼少期に花の蜜を吸ったことがある方も多いかもしれません。そんな馴染みの深いツツジですが、西洋ツツジである「アザレア」とはどういった違いがあるのでしょうか。
アザレアはツツジ特有の色鮮やかな八重咲きが多く、豪華な印象の花で、室内観賞用の品種が秋から出回ります。
ローズマリー、ミント

「ローズマリー」には、脳の活性化やリフレッシュ、血行促進、消化機能の改善、アンチエイジングなどの効能が期待されます。 これらの効能をいかすために、料理やハーブティー、アロマオイルなど、多様な使い方ができるのがローズマリーの特徴です。
「ミント」の香りの健康効果にはどんなものがある?
・メンタルを改善し自律神経を整えてくれる効果
・腸の緊張をほぐし便秘を改善してくれる効果
・花粉症にともなう辛い鼻づまりを軽減してくれる効果
・口内をリフレッシュし、口臭を予防してくれる効果
・女性ならではの悩み、つわりの不快感を和らげてくれる効果
ネモフィラ

入居者のご家族から頂いた、「ネモフィラ」。
漢方ではつぼみの頃に刈り取った地上部を乾燥させたものを白屈菜と称し、特にいぼ取りや、水虫、いんきんたむしといった皮膚疾患、外傷の手当てに対して使用されました。 また煎じて服用すると消炎性鎮痛剤として作用し胃病など内臓疾患に対して効果がある、ともされています。
一覧に戻る
なごみのさと春日西に「ミニ農園」が誕生。ご入居者・スタッフの癒しの場所、みんなが集う拠点に!
老人ホーム敷地内に、プランター型ミニ農園が誕生。ご高齢者と集える拠点になればいいな!とスタッフが育てやすく、花が咲いて食べられる植物を植えていました。そのうち数株が花を咲かせ、葉が茂り、実がなり収穫の時期を迎えています。
ねぎが成長しました

博多万能「ネギ」の葉が成長しました。10本ほどですが食べられる大きさです。ねぎは根を残し、土から4~5cmのところで切ると3~4週間でまた収穫できる大きさに成長します。食材高騰の折、月に1回収穫できるのは助かります。冷凍あさりを買ってあさり汁を作りました。ご入居者に振舞うには少量だったので、一部スタッフのお昼ご飯に提供しました。ラーメンを食べているスタッフにも栄養補給で出しました。
ネギは日本では奈良時代に日本に伝わり、古くから食べられている日本人になじみの深い野菜です。11月~2月頃に旬を迎えます。抗酸化作用の高いビタミンCや硫化アリルが含まれており、風邪予防や血行促進、動脈硬化などの生活習慣病の予防にも効果が期待できます。
ニラも成長

「食べる”お薬”」として有名な「ニラ」
ニラは、古くから薬効のある野菜として知られており、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンEなどの栄養素が豊富に含まれています。ニラを食べるとえられる5つの栄養効果です。
1. 免疫力向上
2. 疲労回復
3. 血流改善
4. 冷え性改善
5. 美肌効果
これらの栄養効果に加え、ニラには骨を丈夫にするカルシウムや、便秘解消に役立つ食物繊維なども豊富に含まれています。
旬の春は特に栄養価が高く、ニラ玉やニラ鍋など、様々な料理に活用できます。
ぜひ積極的にニラを食卓に取り入れて、健康的な体作りを目指しましょう。
チューリップ、セージ、カモミール、トマト

「チューリップ」は見た目だけでなく、香り成分も注目されています。チューリップに含まれる主な香り成分はリナロールという成分です。リナロールは、ラベンダーやベルガモットなど多くの植物にも含まれる成分で、血圧を下げ、鎮静安眠効果があり、抗不安作用が働き、リラックスを促す効果があるとされています。またリナロールの抗不安作用についての研究もありました。チューリップの香りに包まれることで、日々の疲れや緊張感を和らげ、穏やかな気持ちになり、忙しい日常に心の安らぎをもたらしてくれるでしょう。
「セージ」には多くの品種がありますが、ハーブとして市販されているのは主にコモンセージの仲間。ヨモギに似た爽やかな芳香を持ち、わずかに苦みがあります。セージがソーセージの語源になったという説があるくらい、特にソーセージづくりによく使われます。抗菌作用に優れ、うがい薬にすることで口や喉のトラブルを解消し、風邪の予防が期待できるハーブです。
また、ホルモンの乱れによるイライラを鎮める鎮静作用もあります。
ドイツの薬草家は、「セージは、医者、料理人にも、台所や地下室など場所も、貧富も問わず役に立つハーブである」といったそうです
「カモミール」は不眠や不安、また、胃のむかつき、ガス、下痢などの胃腸障害に良いとされています。 また皮膚症状やがん治療に起因する口内炎に局所的に使われることもあります。
アトピー、ニキビ、湿疹、あせも、乾燥などの緩和効果が期待できます。 抜け毛を防いで毛髪にツヤやハリを与える効果もあるため、シャンプーによく利用されます。 風邪の初期症状や月経痛をやわらげる効果 カモミールティーは、体を温め発汗させる作用があるので、風邪の初期症状を緩和する薬茶として利用されています。
真っ赤な「トマト」には栄養がいっぱい。その中でも今とくに注目されているのがリコピンと呼ばれるかカロテノイドの一種。トマトの赤い色はこのリコピンの赤なんです。このリコピンですが、生活習慣病予防や老化抑制にも効果があるとか。もっともその研究は比較的最近はじめられたものでその未知のパワーの全容はすべて解明されているわけではありません。しかし、今までの研究からさまざまなリコピンのパワーが解明されています。
ブルーベリー、アザレア

「ブルーベリー」には、ビタミンC・ビタミンE・アントシアニンなどの強力な抗酸化物質が豊富に含まれます。 これらは、活性酸素を抑え、肌の老化予防にも欠かせない栄養素や機能成分です。 ビタミンCは、肌の構成成分であるコラーゲンの生成に必要なほか、皮膚のメラニン色素の生成を抑える効果もあります。ブルーベリーの効果は次のようです。
1.認知症予防
2.眼精疲労に
3.花粉症の予防
抗酸化物質の中には、アレルギー反応の原因となる「ヒスタミン」を抑える働きが期待されているものも多く存在します。
体が本来もつ免疫力は、加齢とともに低下していきます。
抗酸化物質を意識して摂取し、体がもつ免疫機能の老化を予防することで、花粉症の予防にも繋がるでしょう。
アザレアの花

アザレアの花が咲きました。
「アザレア」は、アゼリアや西洋ツツジやオランダツツジとも呼ばれています。
日本では、ツツジというと花壇に植えられていることも多く、幼少期に花の蜜を吸ったことがある方も多いかもしれません。そんな馴染みの深いツツジですが、西洋ツツジである「アザレア」とはどういった違いがあるのでしょうか。
アザレアはツツジ特有の色鮮やかな八重咲きが多く、豪華な印象の花で、室内観賞用の品種が秋から出回ります。
ローズマリー、ミント

「ローズマリー」には、脳の活性化やリフレッシュ、血行促進、消化機能の改善、アンチエイジングなどの効能が期待されます。 これらの効能をいかすために、料理やハーブティー、アロマオイルなど、多様な使い方ができるのがローズマリーの特徴です。
「ミント」の香りの健康効果にはどんなものがある?
・メンタルを改善し自律神経を整えてくれる効果
・腸の緊張をほぐし便秘を改善してくれる効果
・花粉症にともなう辛い鼻づまりを軽減してくれる効果
・口内をリフレッシュし、口臭を予防してくれる効果
・女性ならではの悩み、つわりの不快感を和らげてくれる効果
ネモフィラ

入居者のご家族から頂いた、「ネモフィラ」。
漢方ではつぼみの頃に刈り取った地上部を乾燥させたものを白屈菜と称し、特にいぼ取りや、水虫、いんきんたむしといった皮膚疾患、外傷の手当てに対して使用されました。 また煎じて服用すると消炎性鎮痛剤として作用し胃病など内臓疾患に対して効果がある、ともされています。