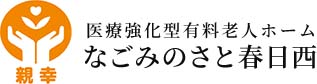2025.3.26
シーパワー ランドパワー
近年、中国の経済発展を受けて「地政学」という学問が注目されています。
学校で習った事はないと思いますが、地政学とは何でしょうか?
地政学は国際政治を考察するにあたって、その地理的条件を重視する学問です。
20世紀初期にかけて形成された伝統的地政学は自国の利益を拡張するための方法論的道具として用いられました。第二次大戦後の国際社会において、地政学という言葉はナチス・ドイツの侵略行為との結びつきから避けられてきました。
台頭する中国

東京外国語語大学、篠田英郎教授が「地政学者」として陸でも海でも覇権を狙う「中国」を指して意外な言葉を残されています。
中国とは、地政学の観点から見てどのような国家か。この問いは現代世界において決定的な重要性を持っている。ところが以外にも簡単には答えられない。
これはいわば「ランド・パワーの雄の覇権交代論」だと答えよう。冷戦時代には、米ソ対立があったが、それが21世紀には米中対立となった。なぜなら中国がソ連より強くなり、ユーラシア大陸でもっとも強くなったからだ、というわけである。
この世界観に従うと、国際政治の構造は、冷戦時代より21世紀とで、あまり変わっていない。依然として、超大国二つの対立構造がある。ただランド・パワー側の最強国家が後退しただけだ。
果たしてこの考えは、地政学の理解として本当に正しいのだろうか?
英米系地政学における中国の位置付け

地政学理論には「英米系地政学」と「大陸系地政学」の二つの大きな流れがある。単に学派の違いというよりも、根本的な世界観の違いに起因した二つの世界観。
「ランド・パワーの覇権交代論」は、世界をランド・パワーとシー・パワーに分ける二元的世界観にもとづいているが、これは「英米式地政学」に特徴的なものと言えます。したがって「ランド・パワーの覇権交代論」は、「英米式地政学」理論の見方を応用したものだと言えます。
英米系地政学の代表といえるハルフォード・マッキンダーは、19世紀の英と露間の「グレート・ゲーム」の世界観に依拠して、日英同盟から日露戦争に至る時に、有名な「歴史の地理的転換軸」を著した。
そのなかで、ロシアの膨張政策を封じ込める大英帝国の政策を、シー・パワーとしての性格がもたらす行動であると説明した。
日英同盟は同じシー・パワーとしての観点から結ばれたとした。またユーラシア大陸とアフリカ大陸が「世界島」を形成し、米国も巨大な島に過ぎないとした。島である以上、米国は、日本やイギリスと並んで、ロシアの拡張政策を封じ込める、シー・パワー政策に合意できると主張した。
マッキンダーの主張に基づき、日本、英国、米国はシー・パワー国としてランド・パワー国、中国を抑止する立場として共有の認識にある。
世界第3位の軍事力をもつ中国

かって近代化に後れを取った国家として存在が危うかった中国は、陸上兵力を中心として軍事力を整備していた。ところが今日の中国は、海軍力についてもめざましい進展を遂げている。陸でも、海でも、覇権国としての地位を固めようとしている。
「ランド・パワーの覇権交代論」は、英米系地政学の浅薄な応用である。中国とロシアは、明らかに異なる性格を持つ。
大陸系地政学は、その代表的理論家カール・ハウスホーファーがヒトラーに影響を与え「生存圏」思想をナチスの主要なドクトリン(教義)とした。大陸系地政学は、「圏域」を重んじる。周辺の小国の領域を「勢力圏」とみなし、影響力を行使する。その結果、世界は幾つかの主要な「圏域」に分断される。
今日の中国とロシアの関係を、覇権国と従属国の関係として描こうとする場合がある。大陸系地政学の世界観にしたがえば、それぞれが独自の「圏域」を持つ。
ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなるBRICSも各大陸の有力国が集まったもので、BRICSは「圏域」思想を意識した多元主義に基づく世界観が、そこにある。
どうなるロシアと中国

中国は、「両生類」(二つの地政学理論に当てはまる)として、英米系地政学理論からの圧力と、大陸系地政学における基盤との両方を強く意識している。「両生類」であるがゆえに、どちらかの思想に完全に傾くということあではしない。ただしあえて言えば、国力の増大とともに、大陸系地政学にもとづいた影響力の拡大に、近年は大きな関心を持っているように見える。
中国には中華帝国の伝統が根強く存在しているとされる。中華思想の特徴は、世界で最も進んだ文明が中国の首都にあり、それが世界の中心とする観念。朝貢制度とは、中国の威光を知る周辺国家が、力の格差を確認する為朝貢品を持って中華帝国の首都に参上する制度である。
中国は、今後も「両生類」の超大国として、「英米系地政学」と「大陸系地政学」の両方に目配りしながら、最終的には中華帝国としての伝統を重視した政策をとっていくだろう。
中国と付き合っていくには、中国が持つ性格と傾向をよく把握しておかねばならない。
漢民族としてのプライド
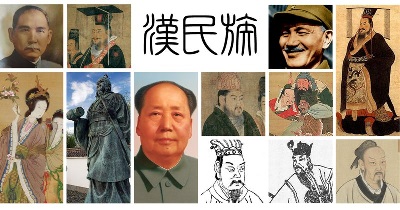 中国は56民族が共同で建国した多民族統一国家です。そのうち漢民族が91%を占め、ほかの55民族の人口が漢民族に比べ少ないことから「少数民族」と呼ばれています。
中国は56民族が共同で建国した多民族統一国家です。そのうち漢民族が91%を占め、ほかの55民族の人口が漢民族に比べ少ないことから「少数民族」と呼ばれています。
例えば、吉林省に多く住む「朝鮮族」は人口192万人、中国内少数民族としても14位。
日本の中国人学生が増えるなかで、漢民族学生が朝鮮族学生に荷物持ちをさせ、差別する姿を見た事があります。
漢民族のプライドは高く、コミュニケーションにおける注意点があります。
1.歴史や戦時に関するはなしはしない
2.宗教に関する話題はさける
3.謝罪させてはいけない
この禁止事項は、外交交渉にも通じています。日中韓の外務大臣会談が実現し、外交関係が改善しつつあります。中国が考える地政学的側面と民族的プライドを考慮しながら振舞う必要があります。
2025年3月22日 日中韓外相会談

中国は不動産バブル崩壊、国有企業倒産などにより2024年12月の若年層都市部失業率は15.7%で、前年同月(14.9%)を上回った。農村部も数億の余剰労働力が存在。
2024年11月中旬、30年ものの国債利回りで、中国が日本を下回りました。背景にあるのは中国の景気減速とデフレ懸念。そして中長期的な成長鈍化です。
コロナ禍以後、中国政府が実施した厳しいゼロコロナ政策により消費低迷、需要不足が発生しました。中国は30年前の日本のバブル崩壊と同じ轍を踏むという予測がされています。
米国企業の中国投資制限、輸入関税率引上など中国への経済制裁は、更なる追い打ちをかけています。
中国に不利な状況下、中国が一時的な日本への歩み寄りをしているだけで、日中の改善がはかられるわけではないと思われます。