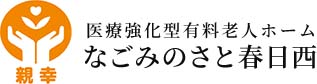2024.9.25
雨上がりのプレゼント
学生時代から作文を褒められていました。大学に入って本格的に小説を書くようになりました。
23歳で結婚して、偶々嫁も文才があり私が書いた小説を編集してくれかなりレベルの高い作品がいくつかあるので紹介します。
「雨上がりのプレゼント」
脇山 博司 (編)脇山 久子

「あっ、そう言えば、今日の夕日見ました?
うろこ雲のキャンパスにオレンジ色がしみ込んで、すごく綺麗だったですよ」
彼はそう言いながら、人通りの少ない夜道の、わたしの少し前を歩いていた。
わたしは何も答えなかった。
なぜならーーー
わたしは彼が誰だか知らないのだから。
たったの二十三分前にはこうなるなんて想像もしていなかった。
いや基本的には、人生の向こう側は、想像通りに進むことはないのだから。
彼はわたしの人生ドラマの中に、すでにキャスティング済みだったのかもしれない。
とりあえず、時計を二十三分前に戻してみる。
《ただいま上下線とも運転を見合わせております。
運転再開の時刻は、未定となっております。
乗客の皆様にはご迷惑をおかけいたしておりますがーーー》
大橋駅ホームでは、五分前から同じアナウンスが流れていた。
これで三度めだ。
それにシンクロするように、わたしも心の中で三度目のため息をつき下を向いた。
そこに見えたのは、裾が雨で濡れた、買ったばかりのパンツスーツと汚れたパンプス。
それを見て、わたしは四度目のため息をついた。
前日から、つい一時間前まで雨が降り続いていた。
そのため、わたしが足止めを食らっている大橋駅と、
わたしが降りる駅である雑餉隈駅の間で線路の一部が陥没。
復旧までの見通しが立っていない状況となっていた。
このとき、大橋駅のホームのベンチでわたしが考えていたこと、
それはーーー何もなかった。
正確に言えば、考えることを体が拒否していた。
ともかく、業を煮やしたわたしは大橋駅の改札を出て、タクシー乗り場へ向かっていた。
いつ動くかわからない電車など待っていられなかったからだ。
だが、そこで見た光景は、タクシーは一台もないのに
待っている乗客が多数という状況。
これでは、こちらもいつになるかわからない。
そもそも財布に残った金額から考えると、タクシーを使うのは厳しいということにもっと早く気付けばよかった。
つまり、わたしに残された唯一の選択肢は、歩いて雑餉隈駅に向かうというものだった。
しかし、そこには大きな問題があった。
実はわたしが大橋駅に降りたのは初めてだったのだ。
わたしがよく知る雑餉隈駅は、たった二駅しか違わないのだが、雰囲気がまるで違っていた。
副都心としてフォーマルに近代化された街、大橋。
古い二階建ての個人商店が並ぶ、下町を代表する雑餉隈。
その雰囲気の違いにわたしは見事なまでにオドオドしていた。
もちろん進むべき方向くらいはわかる。
どう行けばいいのかまるで見当がつかなかった。
だが、人はこういう場合、なぜか皆、同じように考える。
《たったふた駅だ。
とりあえず線路を目印に行けば大丈夫だろう》と。
例に違わず、わたしもその線路が見える道を踏み出した。
が、わたしの物語がおかしくなり始めたのは、ここからーーー
踏み出した右足が地面に着く一歩手前で私の後ろから声がした、この瞬間からであった。

「あのーー」
わたしは体をビクッと震わせた。
それはまるで怯えたリスのようであった。
そして、ゆっくり、慎重に振り返る。
そこにいたのは、エナメルの青いスポーツバッグを斜め掛けにした男子高校生だった。
散髪したばかりなのだろうか、髪は短髪で、爽やかな今時の若者だった。
そして、そのバッグには、《T高校 庭球部》とかかれていた。
十九歳の誕生日を迎えたばかりのわたしより、2、3歳若いだろうか。
彼はーーーいったい誰?
わたしには彼が誰だか、心の引き出しをすべて開けてもわからなかった。
そんなわたしの疑問など無視し、その謎の男子学生は言葉を続けた。
「ーーーもしかしてですけど、井尻駅か雑餉隈駅まで歩いていくんですか?」
「え、あーー、はい」
「やっぱりだ」
彼はそう言って子犬のように笑った。
その狂おしさにも似た無邪気さが、わたしをいっきに不安にした。
「えっと、えっと、失礼します!」
わたしはその場を立ち去ろうとした。
「あ、余計なお世話ですけど」
と謎男子がそれを止め、言葉を続けた。
「この道を進んでも、行き止まりですよ」
「え?」
「まあ、正確に言えば、外環状線が交差しているので、歩道が途切れます。
それから交通量の多い道路に出るんで、夜歩くには、かなり危険ですよ」
わたしは、ただ瞬きの回数が増えていた。
それを気にすることなく、謎男子は線路を挟んだ右側を指差した。
「もし雑餉隈駅まで歩いていくなら、少し遠回りになりますけど
ーーーあそこの右の道、見えますか?」
「あ、うん、じゃなかった、ええ」
「徒歩で行くなら、その道に沿って線路をくぐる様に行った方が、遠回りに見えて一番の近道です」
「え、あ、そのーーーありがとうございます」
「よかったら、僕もこれから雑餉隈駅に向かうんですけど、一緒に行きます?」
わたしは耳を疑った。
どこをどうつながってそういう言葉が出たのか、まるで理解できなかったからだ。
しかし、それ以上に理解できなかったことはーーーその三分後、つまり今に戻るわけだが、
わたしは、その謎男子の一メートル後ろを子供のようについて歩いていたのだ。
これがこの二十三分で起きたことすべて。

そして現在、謎男子は小気味好いスピードで歩を刻み、わたしはただそれについて行き、雑餉隈駅を目指すという状況が生まれていた。
わたしはふと空を見上げていた。
そして、なぜだかこんなことを思った。
《あの星のうちひとつでもいいから地球に落ちてきて、この世界が終わればいいのに》と。
しかし、実際に落ちてきたのは、星ではなく、予想外の言葉であった。
「ーーー好きなんです」
謎男子が言った。
「ーーーえ?」
「この雨上がりの匂いが好きなんです」
「あっーーー、雨の匂い」
「ええ、雨が上がったあとって、いろいろな匂いが鮮明になって、全部リセットされて、なぜか心がすごく落ち着くんです。
まあ、他のやつらには全く共感されないんですけど」
不思議なことにわたしはそれに共感していた。
《雨の匂い》の部分ではない。
自分の好きなものが《他人から共感されない》
という部分にわたしは共感していた。
「突然なんですけど、幸せになる言葉って何か有ります?」
と彼が言った。
「幸せになるーーー言葉?」
「そう。僕にとっての雨上がりの匂いじゃないけど、この言葉が好き、とか、こういう状況がテンションが上がるみたいなやつです」
「そ、そんなこと急に言われても」
「僕の場合だと、花火とか、ロサンゼルスとか、あと、割り箸」
「わ、割り箸?なんで?」
「ほら、割り箸をパッと割ったとき、綺麗に割れると、なんか幸せな気分になりませんか」
「あ、確かに。意外にわかるかも」
「でしょ?」
そのあと、数秒の沈黙が訪れ、パズルピースが一気に埋まっていくような感覚に襲われた。
そして気付けばーーーわたしは笑っていた。
それにワンテンポ遅れ、彼も笑っていた。
なんだか久しぶりに笑った気がした。
こんなに笑ったのがいつぶりか、思い出せないほど久しぶりすぎて、まるで生まれて初めて笑った気がした。
それからほどなくして、今度は二人の間に言葉がなくなった。
打って変って謎男子は何も言葉を発しなくなった。
彼は女性のことはよく知っている。
わたしはそう思った。
女性は心が揺れた時、それを体に行き渡らせ、幸せに変えるだけの時間が必要になる。
それは数秒の時もあるし、まだ出会ったことはないが、一生かけて変換するものもあるだろう。
そして、その変換を行うための、静けさが、わたしの一番好きなものであった。
私は基本、一人でいることが好きだ。
一人の時間を愛している。
ただ、今夜は、二人で好きなものを共有するとこんな気持ちになることを初めて知った。
しかし、その静けさは徐々に消えていく。
そして、それと反比例するように、見覚えのある景色が、目の前にひとつひとつ確実に増えていった。
街灯の明るさが増し、はっきりと雑餉隈駅が見えてきた。
そして、あと数十メートルでゴールというところで、謎男子が言葉を発した。
「ーーースイマセン」
「え、何が?」
「ほら、あれ」
彼は駅の方向を指差した。
そこには雑餉隈駅に到着する電車が見えた。
「結局、運行再開を待っていたほうがよかったですね。
僕のせいで歩かせてしまって申し訳ないです」
「え、そんな、全然!その、なんて言うか、
わたしも楽しかったって言うかーーー」
その言葉を聞いた瞬間、わたしには彼が小さく頷くのが見えた。
ほどなくして、二人は雑餉隈駅についた。 おかしなことだらけではあったが、
終わるとなると、終わることが不自然でおかしなことに思えた。
そして、ずっと見つめていた謎男子の背中が消え、
彼の表情がわたしの目の前に飛び込んできた。
「じゃあ、僕はこれで」
彼は振り返り、そう言った。
「あ、うん。ありがとう」
わたしは小さくうなずいた。
「そう言えば、家は駅の近くなの?」
「いえ、全然、大橋駅の先、高宮駅の近くです」
「え?高宮駅?じゃあ、なんでーーー」
「特に理由はありません。
ーーーーってことにしておいてください」
「え、あ、うん」
と返すのが、私の精一杯であった。
「あ、そうだ、帰りは電車で帰れば?わたしが電車賃出すよ」
「大丈夫です。
初めてあなたを見たときから、ずっと好きだったんです。
初めて好きになった人と、初めて二人で歩いた道を
ーー その人が大好きな静けさを感じながら、また歩いて帰りますから」
そう言って彼は振り返り、今夜ずっと見続けた彼の背中が再び目の前に現れた。
彼は一度も振り返らなかった。
最後まで、彼がどこの誰なのかわからなかった。
もしこれが誰かが書いた物語なら、わたしと彼と、またどこかで出会ったり、 これがキッカケで恋人同士になったり、究極、彼と将来結婚したりするかもしれない。
しかし、実際はこの後、彼とわたしは二度と会わないだろう。
わたしにはそんな時間が残されていない。
なぜなら明日からもう何度目かわからなくなってしまった、九州ガンセンター白血病棟での病院生活に戻らなければならない。
そして今度こそ、そこから出ることはできないだろう。
彼はわたしの物語の最後にわずかに光を与えてくれたが、彼でもわたしにかけられた魔法を解くことはできない。
でも、これが何かしら意味のあるメッセージなのだとしたら、
本当に何もなかったこれまでのわたしの物語を読んでくれた、誰かがくれたプレゼントなのかもしれない。
今夜は、この奇跡のような時間
ーーー あの彼と同じようにどこの誰かもわからない
私の読者から最後に頂いた、 そのプレゼントをゆっくり抱きしめて眠りたいと思う。
一覧に戻る
23歳で結婚して、偶々嫁も文才があり私が書いた小説を編集してくれかなりレベルの高い作品がいくつかあるので紹介します。
「雨上がりのプレゼント」
脇山 博司 (編)脇山 久子

「あっ、そう言えば、今日の夕日見ました?
うろこ雲のキャンパスにオレンジ色がしみ込んで、すごく綺麗だったですよ」
彼はそう言いながら、人通りの少ない夜道の、わたしの少し前を歩いていた。
わたしは何も答えなかった。
なぜならーーー
わたしは彼が誰だか知らないのだから。
たったの二十三分前にはこうなるなんて想像もしていなかった。
いや基本的には、人生の向こう側は、想像通りに進むことはないのだから。
彼はわたしの人生ドラマの中に、すでにキャスティング済みだったのかもしれない。
とりあえず、時計を二十三分前に戻してみる。
《ただいま上下線とも運転を見合わせております。
運転再開の時刻は、未定となっております。
乗客の皆様にはご迷惑をおかけいたしておりますがーーー》
大橋駅ホームでは、五分前から同じアナウンスが流れていた。
これで三度めだ。
それにシンクロするように、わたしも心の中で三度目のため息をつき下を向いた。
そこに見えたのは、裾が雨で濡れた、買ったばかりのパンツスーツと汚れたパンプス。
それを見て、わたしは四度目のため息をついた。
前日から、つい一時間前まで雨が降り続いていた。
そのため、わたしが足止めを食らっている大橋駅と、
わたしが降りる駅である雑餉隈駅の間で線路の一部が陥没。
復旧までの見通しが立っていない状況となっていた。
このとき、大橋駅のホームのベンチでわたしが考えていたこと、
それはーーー何もなかった。
正確に言えば、考えることを体が拒否していた。
ともかく、業を煮やしたわたしは大橋駅の改札を出て、タクシー乗り場へ向かっていた。
いつ動くかわからない電車など待っていられなかったからだ。
だが、そこで見た光景は、タクシーは一台もないのに
待っている乗客が多数という状況。
これでは、こちらもいつになるかわからない。
そもそも財布に残った金額から考えると、タクシーを使うのは厳しいということにもっと早く気付けばよかった。
つまり、わたしに残された唯一の選択肢は、歩いて雑餉隈駅に向かうというものだった。
しかし、そこには大きな問題があった。
実はわたしが大橋駅に降りたのは初めてだったのだ。
わたしがよく知る雑餉隈駅は、たった二駅しか違わないのだが、雰囲気がまるで違っていた。
副都心としてフォーマルに近代化された街、大橋。
古い二階建ての個人商店が並ぶ、下町を代表する雑餉隈。
その雰囲気の違いにわたしは見事なまでにオドオドしていた。
もちろん進むべき方向くらいはわかる。
どう行けばいいのかまるで見当がつかなかった。
だが、人はこういう場合、なぜか皆、同じように考える。
《たったふた駅だ。
とりあえず線路を目印に行けば大丈夫だろう》と。
例に違わず、わたしもその線路が見える道を踏み出した。
が、わたしの物語がおかしくなり始めたのは、ここからーーー
踏み出した右足が地面に着く一歩手前で私の後ろから声がした、この瞬間からであった。

「あのーー」
わたしは体をビクッと震わせた。
それはまるで怯えたリスのようであった。
そして、ゆっくり、慎重に振り返る。
そこにいたのは、エナメルの青いスポーツバッグを斜め掛けにした男子高校生だった。
散髪したばかりなのだろうか、髪は短髪で、爽やかな今時の若者だった。
そして、そのバッグには、《T高校 庭球部》とかかれていた。
十九歳の誕生日を迎えたばかりのわたしより、2、3歳若いだろうか。
彼はーーーいったい誰?
わたしには彼が誰だか、心の引き出しをすべて開けてもわからなかった。
そんなわたしの疑問など無視し、その謎の男子学生は言葉を続けた。
「ーーーもしかしてですけど、井尻駅か雑餉隈駅まで歩いていくんですか?」
「え、あーー、はい」
「やっぱりだ」
彼はそう言って子犬のように笑った。
その狂おしさにも似た無邪気さが、わたしをいっきに不安にした。
「えっと、えっと、失礼します!」
わたしはその場を立ち去ろうとした。
「あ、余計なお世話ですけど」
と謎男子がそれを止め、言葉を続けた。
「この道を進んでも、行き止まりですよ」
「え?」
「まあ、正確に言えば、外環状線が交差しているので、歩道が途切れます。
それから交通量の多い道路に出るんで、夜歩くには、かなり危険ですよ」
わたしは、ただ瞬きの回数が増えていた。
それを気にすることなく、謎男子は線路を挟んだ右側を指差した。
「もし雑餉隈駅まで歩いていくなら、少し遠回りになりますけど
ーーーあそこの右の道、見えますか?」
「あ、うん、じゃなかった、ええ」
「徒歩で行くなら、その道に沿って線路をくぐる様に行った方が、遠回りに見えて一番の近道です」
「え、あ、そのーーーありがとうございます」
「よかったら、僕もこれから雑餉隈駅に向かうんですけど、一緒に行きます?」
わたしは耳を疑った。
どこをどうつながってそういう言葉が出たのか、まるで理解できなかったからだ。
しかし、それ以上に理解できなかったことはーーーその三分後、つまり今に戻るわけだが、
わたしは、その謎男子の一メートル後ろを子供のようについて歩いていたのだ。
これがこの二十三分で起きたことすべて。

そして現在、謎男子は小気味好いスピードで歩を刻み、わたしはただそれについて行き、雑餉隈駅を目指すという状況が生まれていた。
わたしはふと空を見上げていた。
そして、なぜだかこんなことを思った。
《あの星のうちひとつでもいいから地球に落ちてきて、この世界が終わればいいのに》と。
しかし、実際に落ちてきたのは、星ではなく、予想外の言葉であった。
「ーーー好きなんです」
謎男子が言った。
「ーーーえ?」
「この雨上がりの匂いが好きなんです」
「あっーーー、雨の匂い」
「ええ、雨が上がったあとって、いろいろな匂いが鮮明になって、全部リセットされて、なぜか心がすごく落ち着くんです。
まあ、他のやつらには全く共感されないんですけど」
不思議なことにわたしはそれに共感していた。
《雨の匂い》の部分ではない。
自分の好きなものが《他人から共感されない》
という部分にわたしは共感していた。
「突然なんですけど、幸せになる言葉って何か有ります?」
と彼が言った。
「幸せになるーーー言葉?」
「そう。僕にとっての雨上がりの匂いじゃないけど、この言葉が好き、とか、こういう状況がテンションが上がるみたいなやつです」
「そ、そんなこと急に言われても」
「僕の場合だと、花火とか、ロサンゼルスとか、あと、割り箸」
「わ、割り箸?なんで?」
「ほら、割り箸をパッと割ったとき、綺麗に割れると、なんか幸せな気分になりませんか」
「あ、確かに。意外にわかるかも」
「でしょ?」
そのあと、数秒の沈黙が訪れ、パズルピースが一気に埋まっていくような感覚に襲われた。
そして気付けばーーーわたしは笑っていた。
それにワンテンポ遅れ、彼も笑っていた。
なんだか久しぶりに笑った気がした。
こんなに笑ったのがいつぶりか、思い出せないほど久しぶりすぎて、まるで生まれて初めて笑った気がした。
それからほどなくして、今度は二人の間に言葉がなくなった。
打って変って謎男子は何も言葉を発しなくなった。
彼は女性のことはよく知っている。
わたしはそう思った。
女性は心が揺れた時、それを体に行き渡らせ、幸せに変えるだけの時間が必要になる。
それは数秒の時もあるし、まだ出会ったことはないが、一生かけて変換するものもあるだろう。
そして、その変換を行うための、静けさが、わたしの一番好きなものであった。
私は基本、一人でいることが好きだ。
一人の時間を愛している。
ただ、今夜は、二人で好きなものを共有するとこんな気持ちになることを初めて知った。
しかし、その静けさは徐々に消えていく。
そして、それと反比例するように、見覚えのある景色が、目の前にひとつひとつ確実に増えていった。
街灯の明るさが増し、はっきりと雑餉隈駅が見えてきた。
そして、あと数十メートルでゴールというところで、謎男子が言葉を発した。
「ーーースイマセン」
「え、何が?」
「ほら、あれ」
彼は駅の方向を指差した。
そこには雑餉隈駅に到着する電車が見えた。
「結局、運行再開を待っていたほうがよかったですね。
僕のせいで歩かせてしまって申し訳ないです」
「え、そんな、全然!その、なんて言うか、
わたしも楽しかったって言うかーーー」
その言葉を聞いた瞬間、わたしには彼が小さく頷くのが見えた。
ほどなくして、二人は雑餉隈駅についた。 おかしなことだらけではあったが、
終わるとなると、終わることが不自然でおかしなことに思えた。
そして、ずっと見つめていた謎男子の背中が消え、
彼の表情がわたしの目の前に飛び込んできた。
「じゃあ、僕はこれで」
彼は振り返り、そう言った。
「あ、うん。ありがとう」
わたしは小さくうなずいた。
「そう言えば、家は駅の近くなの?」
「いえ、全然、大橋駅の先、高宮駅の近くです」
「え?高宮駅?じゃあ、なんでーーー」
「特に理由はありません。
ーーーーってことにしておいてください」
「え、あ、うん」
と返すのが、私の精一杯であった。
「あ、そうだ、帰りは電車で帰れば?わたしが電車賃出すよ」
「大丈夫です。
初めてあなたを見たときから、ずっと好きだったんです。
初めて好きになった人と、初めて二人で歩いた道を
ーー その人が大好きな静けさを感じながら、また歩いて帰りますから」
そう言って彼は振り返り、今夜ずっと見続けた彼の背中が再び目の前に現れた。
彼は一度も振り返らなかった。
最後まで、彼がどこの誰なのかわからなかった。
もしこれが誰かが書いた物語なら、わたしと彼と、またどこかで出会ったり、 これがキッカケで恋人同士になったり、究極、彼と将来結婚したりするかもしれない。
しかし、実際はこの後、彼とわたしは二度と会わないだろう。
わたしにはそんな時間が残されていない。
なぜなら明日からもう何度目かわからなくなってしまった、九州ガンセンター白血病棟での病院生活に戻らなければならない。
そして今度こそ、そこから出ることはできないだろう。
彼はわたしの物語の最後にわずかに光を与えてくれたが、彼でもわたしにかけられた魔法を解くことはできない。
でも、これが何かしら意味のあるメッセージなのだとしたら、
本当に何もなかったこれまでのわたしの物語を読んでくれた、誰かがくれたプレゼントなのかもしれない。
今夜は、この奇跡のような時間
ーーー あの彼と同じようにどこの誰かもわからない
私の読者から最後に頂いた、 そのプレゼントをゆっくり抱きしめて眠りたいと思う。