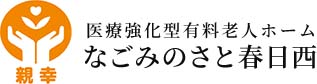2025.4.12
介護福祉会士会3月
(日本介護福祉士会ホームページより)

お知らせ
令和7年3月28日。福岡厚生労働大臣に対し、要望書を提出しました
令和7年3月28日。及川会長が、厚生労働省を往訪し、日原社会・援護局長に対し、福岡厚生労働大臣宛の要望書を提出しました。
及川会長は、介護福祉士資格が、介護を仕事する方にとって真に目指す資格としてい位置づくためにも、資格取得方法の一元化は確実に完全実施していただきたい旨。要請しました。
また、種々意見交換をするなかで、日原局長から、当会が国の補助事業で実施した「外国人介護人材のための介護福祉士国家資格取得支援講座」について、単に資格を取得することが大事なのではなく、その経過で「学習することの意味」や「資格を取得することの意味」を理解することも大切だと理解した旨。発言がありました。
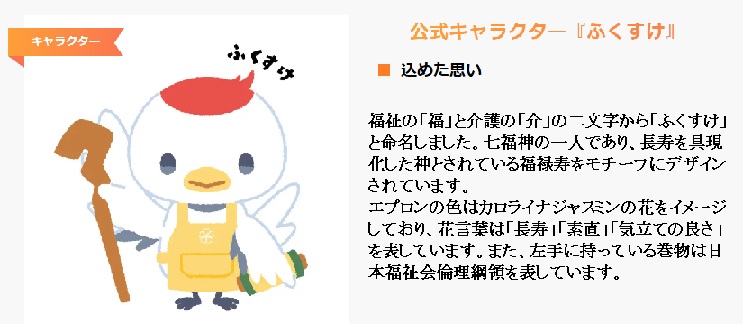
令和7年3月24日。及川会長が第245回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました
今回の介護給付費分科会では、
1.令和6年度介護従事者処遇状況等調査の結果について、
2.今後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて、
3.外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告)、
4.令和6年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)、
5.その他、
の議論がおこなわれました。
及川会長は、介護従事者の処遇状況等調査の結果について、介護職員の処遇については、確かに改善しているが、参考資料を見れば、全産業平均とはかなり大きな開きがあり、全産業の有効求人倍率が約1倍で推移しているなかで、介護関係職種の有効求人倍率が高い水準に留まっている状況がある。これを踏まえると、十分な処遇改善が図られているとは言えないと考えており、介護に関連する皆様のより適切な評価が必要であると考えている旨。発言しました。
また、今後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについては、現在でも、新型コロナウイルス感染症が高齢者にとって負担が大きく、命にも関わるものと理解したうえで、感染拡大防止のため、以前と変わらない丁寧な対応を行っていると承知している。今回は、一部、臨時的な取扱の延長に係る議論が提案されているが、対応案にあるように、臨時的取扱を廃止することにより、介護サービスの継続的・安定的運営に大きな影響が生じうるものや感染した利用者に不利益が生じうるものについては、継続的な取扱とする必要があると考える旨。発言しました。
さらに、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、示された全ての項目を遵守することは事業者として当然であるが、一方でサービス提供責任者に求められる役割がますます大きくなる。サービス提供責任者の質を担保するための「サービス提供責任者の要件の在り方」や「研修の在り方」等についても検討する必要がある。なお、小規模多機能型居宅介護サービスにおいて実施される訪問サービスの従事者についても、5つの遵守事項はすべて取り入れるべきである。また、外国人介護人材に係る人員配置基準上の関係では、外国人介護人材が訪問系サービスの提供に当たっては、外国人介護人材が訪問系サービスを一人で適切に行うことができるよう、一定期間、サービス提供責任者等の同行が必要である。このことを踏まえれば、在留資格の種類によらず、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができると判断されてから職員数に算入することとするのが妥当ではないかと考える旨。等について発言しました。
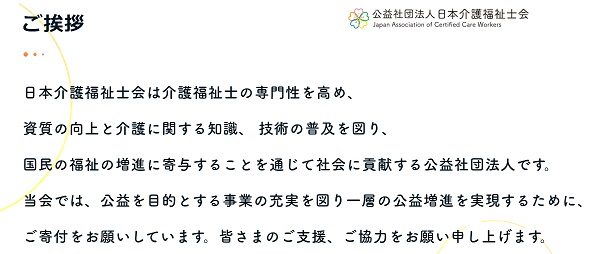
令和7年3月17日。及川会長が第118回社会保障審議会介護保険部会に出席しました
今回の介護保険部会では、
1.地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まい支援について、
2.その他(介護情報基盤について、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について)、
の議論がおこなわれました。
及川会長は、地域包括ケアシステムにおける高齢者の住まいについて、超高齢社会が進展する現在、またこれからの社会において住まいの確保は重要な課題であることは理解できる、としたうえで、資料中「現状・課題」の中で、「介護保険事業(支援)計画で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるにあたり、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は約30%にとどまっており、更なる実効性の確保が課題」とされているが、サービス需要の捉え方はなかなか難しい。一人ひとりの望まれる生活がある中で、やむを得ない結果としてなされた住まいの選択もあると想定され、サ高住等の供給量の捉え方は一定の工夫が必要と考える旨。発言しました。
他方で、サ高住や住宅型有料などの高齢者住宅には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に配置されている入居を検討する際の窓口であり、サービスの説明などを行う生活相談員等の配置は義務付けられていない。要介護状態となった高齢者やその家族等にとって、この介護保険サービス等の理解はなかなか難しいと聞く。本人の自由な選択と意思決定が確保される環境整備は特に重要な課題である。としたうえで、需要量を正しく把握するためにも、地域住民のニーズに正しく向き合うためにも、福祉の視点を備えた専門職を活用することを検討すべきである旨。発言しました。
また、及川会長は、介護サービスや住まいの選択において、専門職の適切な関与を考える際に、資料にある、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、これからのニーズに応えるサービスと考えてよいのか。また、現在の利用実態等を教えてほしい旨。質問しました。
これに対し、厚生労働省からは、実施自治体の大多数は「生活援助員派遣事業」としての活用であり、「居住支援」を行っているのは、6治体に留まっている。ただし、本事業は、改正住宅セーフティネット法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨を明確化するなどの実施要綱の見直しを行ったところであり、居住支援に取り組む自治体への伴走支援を行う「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」を活用しつつ、本事業の実施自治体数の増加を図っていく予定である旨。ただし、当該事業だけで達成できるものではなく、関係部局と連携して課題に取り組んでまいりたい旨。の回答がありました。
更に、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、示された全ての項目を遵守することは事業者として当然であるが、一方でサービス提供責任者に求められる役割がますます大きくなることに懸念を持つ。としたうえで、サービス提供責任者の質を担保するための「サービス提供責任者の要件の在り方」や「研修の在り方」等についても検討する必要がある旨。小規模多機能型居宅介護サービスにおいて実施される訪問サービスの従事者についても、5つの遵守事項はすべて取り入れるべきと考えている旨。等について発言しました。
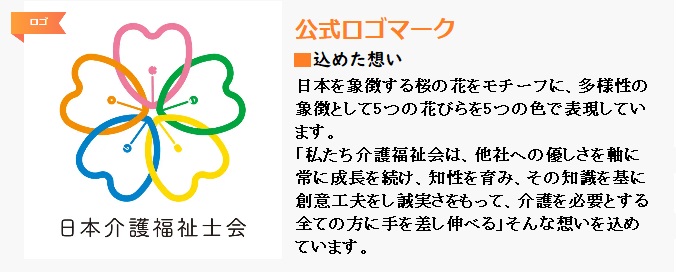
令和7年3月3日。今村副会長が第21回医療介護総合確保促進会議に出席しました
今回の会議では、
1.地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和5年度交付状況等及び令和6年度内示状況について(報告)、
2.医療法等の一部を改正する法律案について(報告)、
3.令和5年の地方からの提案等に関する対応について、
の議論がおこなわれました。
今村副会長は、医療法等の一部を改正する法律案(報告)を踏まえ、改正の趣旨で示されている高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少について、すでに都道府県単位で将来予測に基づく対策等を医療・介護の事業計画の中で策定し実施していると承知しているが、執行状況や基金事業における取組及び事後評価を見ると、特に介護分野においてはアウトプット指標に対する実績が充分達成できている状況は少ない。本基金は、基金の対象事業に関する市町村計画を都道府県がまとめ都道府県計画として国へ提出され、それぞれの事業が実施されているが、2040年を見据えた医療介護提供体制を確保するためには各事業の達成率を上げていかなければならない。としたうえで、2040年に向けた医療や介護サービスの提供体制等の在り方に関する検討会や医療介護DBを用いた研究等が行われているが、将来予測は都道府県ではもちろん、市町村単位でも大きく違うことを踏まえつつ、こういった検討会や研究等で示されているデータ等を活用した事業計画と実施を期待したい旨。発言しました。
また、近年、介護分野においては介護従事者の確保に関する事業の割合が増えていることは、都道府県としても人材確保に関して大きな課題意識を持っているものと認識している。しかし介護サービスを提供する事業者や現場の当事者は更に強い危機感を持ちつつ、人材の確保と介護の質の担保を同時並行でおこなうため、工夫や取組を重ね、日々事業を運営している。それでもサービスの提供が困難となり、事業の撤退や廃業などが報道等でも相次いでいる状況にある。これは必要なサービスを受けることができなくなる、いわゆる介護難民が増えていくことを意味し、早急な改善を目に見える形で示していかなければならず、人材確保については都道府県の取組等に対し、更に強化できるよう国としての後押しをお願いする旨。発言しました。
更に、地域医療構想が見直されることは、都道府県民の生活等に関する重要なことであるが、地域住民としても、将来に向けて都道府県がおこなっている医療・介護について、今のうちから知っておくべきこととして、地域医療介護総合確保基金の概要や事業に関する周知広報と取組結果の公表などを充実させることも必要である。この都道府県計画等を通じた地域住民への理解促進は、地域包括ケアの更なる推進・深化を図る上では重要であり、我々職能団体としても、今後の地域を支える介護人材として、例えばリタイアメントした介護福祉士が更に活躍できないか、こういった視点も含めた検討を進めているところである。2040年に向けて、医療・介護サービスの提供体制を確保する為には、それぞれの地域において将来予測を見据えた事業等を効果的に実施していかなければならず、その為には都道府県単位でも活動している施設団体や我々職能団体との連携等は必須であり、国からの都道府県への働きかけを強くお願いしたい旨。等について発言しました。
一覧に戻る

お知らせ
令和7年3月28日。福岡厚生労働大臣に対し、要望書を提出しました
令和7年3月28日。及川会長が、厚生労働省を往訪し、日原社会・援護局長に対し、福岡厚生労働大臣宛の要望書を提出しました。
及川会長は、介護福祉士資格が、介護を仕事する方にとって真に目指す資格としてい位置づくためにも、資格取得方法の一元化は確実に完全実施していただきたい旨。要請しました。
また、種々意見交換をするなかで、日原局長から、当会が国の補助事業で実施した「外国人介護人材のための介護福祉士国家資格取得支援講座」について、単に資格を取得することが大事なのではなく、その経過で「学習することの意味」や「資格を取得することの意味」を理解することも大切だと理解した旨。発言がありました。
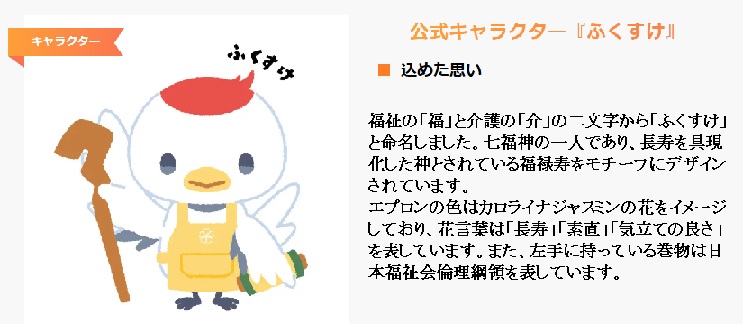
令和7年3月24日。及川会長が第245回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました
今回の介護給付費分科会では、
1.令和6年度介護従事者処遇状況等調査の結果について、
2.今後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて、
3.外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告)、
4.令和6年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の検討結果について(報告)、
5.その他、
の議論がおこなわれました。
及川会長は、介護従事者の処遇状況等調査の結果について、介護職員の処遇については、確かに改善しているが、参考資料を見れば、全産業平均とはかなり大きな開きがあり、全産業の有効求人倍率が約1倍で推移しているなかで、介護関係職種の有効求人倍率が高い水準に留まっている状況がある。これを踏まえると、十分な処遇改善が図られているとは言えないと考えており、介護に関連する皆様のより適切な評価が必要であると考えている旨。発言しました。
また、今後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについては、現在でも、新型コロナウイルス感染症が高齢者にとって負担が大きく、命にも関わるものと理解したうえで、感染拡大防止のため、以前と変わらない丁寧な対応を行っていると承知している。今回は、一部、臨時的な取扱の延長に係る議論が提案されているが、対応案にあるように、臨時的取扱を廃止することにより、介護サービスの継続的・安定的運営に大きな影響が生じうるものや感染した利用者に不利益が生じうるものについては、継続的な取扱とする必要があると考える旨。発言しました。
さらに、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、示された全ての項目を遵守することは事業者として当然であるが、一方でサービス提供責任者に求められる役割がますます大きくなる。サービス提供責任者の質を担保するための「サービス提供責任者の要件の在り方」や「研修の在り方」等についても検討する必要がある。なお、小規模多機能型居宅介護サービスにおいて実施される訪問サービスの従事者についても、5つの遵守事項はすべて取り入れるべきである。また、外国人介護人材に係る人員配置基準上の関係では、外国人介護人材が訪問系サービスの提供に当たっては、外国人介護人材が訪問系サービスを一人で適切に行うことができるよう、一定期間、サービス提供責任者等の同行が必要である。このことを踏まえれば、在留資格の種類によらず、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができると判断されてから職員数に算入することとするのが妥当ではないかと考える旨。等について発言しました。
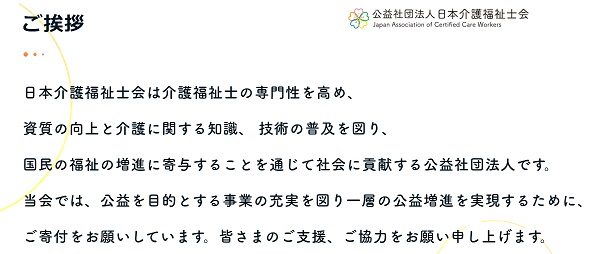
令和7年3月17日。及川会長が第118回社会保障審議会介護保険部会に出席しました
今回の介護保険部会では、
1.地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まい支援について、
2.その他(介護情報基盤について、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について)、
の議論がおこなわれました。
及川会長は、地域包括ケアシステムにおける高齢者の住まいについて、超高齢社会が進展する現在、またこれからの社会において住まいの確保は重要な課題であることは理解できる、としたうえで、資料中「現状・課題」の中で、「介護保険事業(支援)計画で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるにあたり、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は約30%にとどまっており、更なる実効性の確保が課題」とされているが、サービス需要の捉え方はなかなか難しい。一人ひとりの望まれる生活がある中で、やむを得ない結果としてなされた住まいの選択もあると想定され、サ高住等の供給量の捉え方は一定の工夫が必要と考える旨。発言しました。
他方で、サ高住や住宅型有料などの高齢者住宅には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に配置されている入居を検討する際の窓口であり、サービスの説明などを行う生活相談員等の配置は義務付けられていない。要介護状態となった高齢者やその家族等にとって、この介護保険サービス等の理解はなかなか難しいと聞く。本人の自由な選択と意思決定が確保される環境整備は特に重要な課題である。としたうえで、需要量を正しく把握するためにも、地域住民のニーズに正しく向き合うためにも、福祉の視点を備えた専門職を活用することを検討すべきである旨。発言しました。
また、及川会長は、介護サービスや住まいの選択において、専門職の適切な関与を考える際に、資料にある、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、これからのニーズに応えるサービスと考えてよいのか。また、現在の利用実態等を教えてほしい旨。質問しました。
これに対し、厚生労働省からは、実施自治体の大多数は「生活援助員派遣事業」としての活用であり、「居住支援」を行っているのは、6治体に留まっている。ただし、本事業は、改正住宅セーフティネット法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨を明確化するなどの実施要綱の見直しを行ったところであり、居住支援に取り組む自治体への伴走支援を行う「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」を活用しつつ、本事業の実施自治体数の増加を図っていく予定である旨。ただし、当該事業だけで達成できるものではなく、関係部局と連携して課題に取り組んでまいりたい旨。の回答がありました。
更に、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、示された全ての項目を遵守することは事業者として当然であるが、一方でサービス提供責任者に求められる役割がますます大きくなることに懸念を持つ。としたうえで、サービス提供責任者の質を担保するための「サービス提供責任者の要件の在り方」や「研修の在り方」等についても検討する必要がある旨。小規模多機能型居宅介護サービスにおいて実施される訪問サービスの従事者についても、5つの遵守事項はすべて取り入れるべきと考えている旨。等について発言しました。
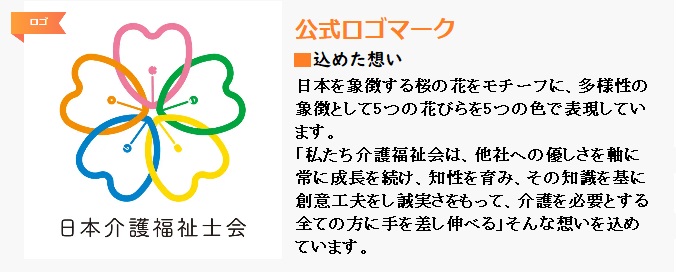
令和7年3月3日。今村副会長が第21回医療介護総合確保促進会議に出席しました
今回の会議では、
1.地域医療介護総合確保基金の執行状況、令和5年度交付状況等及び令和6年度内示状況について(報告)、
2.医療法等の一部を改正する法律案について(報告)、
3.令和5年の地方からの提案等に関する対応について、
の議論がおこなわれました。
今村副会長は、医療法等の一部を改正する法律案(報告)を踏まえ、改正の趣旨で示されている高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少について、すでに都道府県単位で将来予測に基づく対策等を医療・介護の事業計画の中で策定し実施していると承知しているが、執行状況や基金事業における取組及び事後評価を見ると、特に介護分野においてはアウトプット指標に対する実績が充分達成できている状況は少ない。本基金は、基金の対象事業に関する市町村計画を都道府県がまとめ都道府県計画として国へ提出され、それぞれの事業が実施されているが、2040年を見据えた医療介護提供体制を確保するためには各事業の達成率を上げていかなければならない。としたうえで、2040年に向けた医療や介護サービスの提供体制等の在り方に関する検討会や医療介護DBを用いた研究等が行われているが、将来予測は都道府県ではもちろん、市町村単位でも大きく違うことを踏まえつつ、こういった検討会や研究等で示されているデータ等を活用した事業計画と実施を期待したい旨。発言しました。
また、近年、介護分野においては介護従事者の確保に関する事業の割合が増えていることは、都道府県としても人材確保に関して大きな課題意識を持っているものと認識している。しかし介護サービスを提供する事業者や現場の当事者は更に強い危機感を持ちつつ、人材の確保と介護の質の担保を同時並行でおこなうため、工夫や取組を重ね、日々事業を運営している。それでもサービスの提供が困難となり、事業の撤退や廃業などが報道等でも相次いでいる状況にある。これは必要なサービスを受けることができなくなる、いわゆる介護難民が増えていくことを意味し、早急な改善を目に見える形で示していかなければならず、人材確保については都道府県の取組等に対し、更に強化できるよう国としての後押しをお願いする旨。発言しました。
更に、地域医療構想が見直されることは、都道府県民の生活等に関する重要なことであるが、地域住民としても、将来に向けて都道府県がおこなっている医療・介護について、今のうちから知っておくべきこととして、地域医療介護総合確保基金の概要や事業に関する周知広報と取組結果の公表などを充実させることも必要である。この都道府県計画等を通じた地域住民への理解促進は、地域包括ケアの更なる推進・深化を図る上では重要であり、我々職能団体としても、今後の地域を支える介護人材として、例えばリタイアメントした介護福祉士が更に活躍できないか、こういった視点も含めた検討を進めているところである。2040年に向けて、医療・介護サービスの提供体制を確保する為には、それぞれの地域において将来予測を見据えた事業等を効果的に実施していかなければならず、その為には都道府県単位でも活動している施設団体や我々職能団体との連携等は必須であり、国からの都道府県への働きかけを強くお願いしたい旨。等について発言しました。