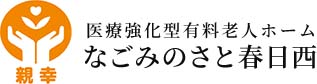2025.4.17
傾聴力をつけよう
「傾聴力」とは?介護職の必須スキル「傾聴」の意味と上達ポイント
ケアコンサルタント(看護師・介護支援専門員) 川上 由里子さんによる介護職必須のコミュニケーションスキル「傾聴」のご紹介です。
「傾聴」とは積極的なコミュニケーション
「きく」ことの言葉の意味は漢字によって異なり、きき方によって相手とのコミュニケーションや関係性も異なります。3つの「きく」について見てみましょう。
【訊く】ask 尋ねる、問う、取り調べる
【聞く】hear 聞こえる 聞いている 声が耳に入る
【聴く】listen 聴こうと努力する 相手の言いたいことを聴く
「傾聴」とは相手の話をじっくり共感的に聴くことをいいます。「ただきいている」といった受身的な行動ではなく、積極的、能動的なコミュニケ−ションです。介護職や看護職が目指す「傾聴」とは、話し手のペースに寄り添い積極的な関心を示し共感的に【聴く】(listen)ことです。
介護において積極的な「傾聴」が大切な理由
介護をする上で、何故「傾聴」が大切なのでしょうか。人は相手に対して信頼感がないと、「この人に話したくない」「この人に介護されたくない」と防衛の気持ちが強くなります。
以前、介護施設でこんなことがありました。新人の介護職員だとトイレまで歩き、ベテランの介護職員だと車椅子でトイレに行かれる方がいました。なぜだろう?とその方にお話を伺うと、「新人の職員さんはいつも私の体調を聴いてくれるの。前に転んだことも知っているので心強いわ」とおっしゃいました。
積極的な傾聴は、自分を受け入れてくれる、自分を理解しようとしてくれるという安心感が生まれ、信頼関係を築くことにつながります。信頼関係が生まれると介護にも協力してもらえるようになり、介護者にとっても大きなメリットになるのです。
「傾聴」における効果とは?

次に傾聴にはどんな効果があるか詳しくみていきましょう?傾聴は相手を受け入れ見守る「抱える」機能と、相手が意識していなかったものを引き出し意識化させる「揺さぶる」機能があります。その2つの機能により下記の効果が期待できます。
「傾聴」の効果
信頼関係が高まる
不安や悩みを分かち合える人という安心感を持つ。
自己理解が進む
話し手も自分の気持ちや考えに気づき自己理解が進む。
カタルシス効果と自己受容の促進
安心感を持てると話すことが促進され、胸のうちにたまっていたものを吐き出すことができる。
誠実に相手の立場を理解しようとしながら聴くことは、このように大きな効果を生みます。「傾聴」は看護や介護の現場だけでなく、人間関係のどんな場面でも有効です。
これで「傾聴」が上達!「傾聴」に必要な3つの基本的態度・ポイント
傾聴をするとき、私たちに必要とされる態度があります。カール・ロジャースは聴き手の基本的態度として3つの条件をあげています。
聴き手にとって重要なことは、相手の気持ちに寄り添うことです。話し手が何と言っているのかではなく、何を言いたいのかを理解することが大切です。
1.自己一致
自分自身があるがままで構えのない自分でいること。自分の感情を否定せずに受け止められると、相手に対し誠実、純粋な態度となります。
2.無条件の肯定的配慮
相手をかけがえのない独自の存在として尊重し受容すること。話の内容とは関係なく、平等に一人の人間として接します。
3.共感的理解
相手の主観的な見方、感じ方、考え方を、その人のように見たり、感じたり、考えたりします。
必見!介護職に必要な4つの「傾聴」技法

傾聴の技法はあくまでも傾聴の心構えがあってのことですが、私自身も傾聴の練習で得た技法を実践することで、人間関係が良い方向に変わりましたのでご紹介します。
1.簡単受容
相手の話をさえぎらずに「うなずき」「あいづち」「繰り返し」。「繰り返し」とは相手の話のキーワードの1~2語を聴き手が同じ言葉で繰り返す。寄り添っていることを示す。
2.感情への応答
感情的な表現を聴き取り、それを伝え返す。話し手は自分の気持ちに気づき、わかってもらえたという安心感を持つ。
3.要約
長くなり混乱しがちな話を簡潔に要約して伝え返す。話し手が考えをまとめ、見直すことを援助する。
4.質問(開かれた質問)
話し手が自由に回答できるような質問をする。聴き手が話し手に関心を持っていることを示し、話し手は自分自身の理解が深まる。
話し手の主訴に耳を傾けよう
高齢者や不安や痛みを抱えた人は、話せない思いや遠慮など相談しにくい背景を抱えています。不安や戸惑い、心配ごとに対して介護職が関わることができる「傾聴」は、思いやりのあるコミュニケーションです。職業に、人生に、対人関係に、改めて意識して心の耳を傾けてみましょう。
一覧に戻る
ケアコンサルタント(看護師・介護支援専門員) 川上 由里子さんによる介護職必須のコミュニケーションスキル「傾聴」のご紹介です。
「傾聴」とは積極的なコミュニケーション
「きく」ことの言葉の意味は漢字によって異なり、きき方によって相手とのコミュニケーションや関係性も異なります。3つの「きく」について見てみましょう。
【訊く】ask 尋ねる、問う、取り調べる
【聞く】hear 聞こえる 聞いている 声が耳に入る
【聴く】listen 聴こうと努力する 相手の言いたいことを聴く
「傾聴」とは相手の話をじっくり共感的に聴くことをいいます。「ただきいている」といった受身的な行動ではなく、積極的、能動的なコミュニケ−ションです。介護職や看護職が目指す「傾聴」とは、話し手のペースに寄り添い積極的な関心を示し共感的に【聴く】(listen)ことです。
介護において積極的な「傾聴」が大切な理由
介護をする上で、何故「傾聴」が大切なのでしょうか。人は相手に対して信頼感がないと、「この人に話したくない」「この人に介護されたくない」と防衛の気持ちが強くなります。
以前、介護施設でこんなことがありました。新人の介護職員だとトイレまで歩き、ベテランの介護職員だと車椅子でトイレに行かれる方がいました。なぜだろう?とその方にお話を伺うと、「新人の職員さんはいつも私の体調を聴いてくれるの。前に転んだことも知っているので心強いわ」とおっしゃいました。
積極的な傾聴は、自分を受け入れてくれる、自分を理解しようとしてくれるという安心感が生まれ、信頼関係を築くことにつながります。信頼関係が生まれると介護にも協力してもらえるようになり、介護者にとっても大きなメリットになるのです。
「傾聴」における効果とは?

次に傾聴にはどんな効果があるか詳しくみていきましょう?傾聴は相手を受け入れ見守る「抱える」機能と、相手が意識していなかったものを引き出し意識化させる「揺さぶる」機能があります。その2つの機能により下記の効果が期待できます。
「傾聴」の効果
信頼関係が高まる
不安や悩みを分かち合える人という安心感を持つ。
自己理解が進む
話し手も自分の気持ちや考えに気づき自己理解が進む。
カタルシス効果と自己受容の促進
安心感を持てると話すことが促進され、胸のうちにたまっていたものを吐き出すことができる。
誠実に相手の立場を理解しようとしながら聴くことは、このように大きな効果を生みます。「傾聴」は看護や介護の現場だけでなく、人間関係のどんな場面でも有効です。
これで「傾聴」が上達!「傾聴」に必要な3つの基本的態度・ポイント
傾聴をするとき、私たちに必要とされる態度があります。カール・ロジャースは聴き手の基本的態度として3つの条件をあげています。
聴き手にとって重要なことは、相手の気持ちに寄り添うことです。話し手が何と言っているのかではなく、何を言いたいのかを理解することが大切です。
1.自己一致
自分自身があるがままで構えのない自分でいること。自分の感情を否定せずに受け止められると、相手に対し誠実、純粋な態度となります。
2.無条件の肯定的配慮
相手をかけがえのない独自の存在として尊重し受容すること。話の内容とは関係なく、平等に一人の人間として接します。
3.共感的理解
相手の主観的な見方、感じ方、考え方を、その人のように見たり、感じたり、考えたりします。
必見!介護職に必要な4つの「傾聴」技法

傾聴の技法はあくまでも傾聴の心構えがあってのことですが、私自身も傾聴の練習で得た技法を実践することで、人間関係が良い方向に変わりましたのでご紹介します。
1.簡単受容
相手の話をさえぎらずに「うなずき」「あいづち」「繰り返し」。「繰り返し」とは相手の話のキーワードの1~2語を聴き手が同じ言葉で繰り返す。寄り添っていることを示す。
2.感情への応答
感情的な表現を聴き取り、それを伝え返す。話し手は自分の気持ちに気づき、わかってもらえたという安心感を持つ。
3.要約
長くなり混乱しがちな話を簡潔に要約して伝え返す。話し手が考えをまとめ、見直すことを援助する。
4.質問(開かれた質問)
話し手が自由に回答できるような質問をする。聴き手が話し手に関心を持っていることを示し、話し手は自分自身の理解が深まる。
話し手の主訴に耳を傾けよう
高齢者や不安や痛みを抱えた人は、話せない思いや遠慮など相談しにくい背景を抱えています。不安や戸惑い、心配ごとに対して介護職が関わることができる「傾聴」は、思いやりのあるコミュニケーションです。職業に、人生に、対人関係に、改めて意識して心の耳を傾けてみましょう。